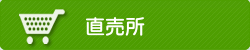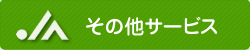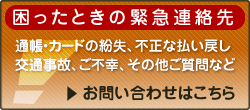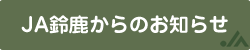[楽しい園芸・野菜のルーツ] [ベジタブルライフ] [私の食育日記] [バックナンバー]
楽しい園芸 – プロから聞いたアドバイスを紹介。初めての人もおまかせ! –
【あなたもチャレンジ!家庭菜園】カボチャ 強健で育てやすい
園芸研究家 ●成松次郎
 生育適温は17~20度でウリ科野菜の中では比較的低温に強く、強健で病害虫も比較的少ない野菜です。ビタミン類、カリウム、カルシウムなどを豊富に含み、特に免疫力を高めるβ-カロテン含量は野菜の中ではトップクラスです。
生育適温は17~20度でウリ科野菜の中では比較的低温に強く、強健で病害虫も比較的少ない野菜です。ビタミン類、カリウム、カルシウムなどを豊富に含み、特に免疫力を高めるβ-カロテン含量は野菜の中ではトップクラスです。
[品種]
西洋カボチャでは「みやこ」(サカタのタネ)、「えびす」(タキイ種苗)、「九重栗」(カネコ種苗)など、ミニカボチャでは「坊ちゃん」(ヴィルモランみかど)など。表皮が白く貯蔵性のある「雪化粧」(サカタのタネ)などもあります。
[苗作り]
種は一般地では3、4月に12cmポットに3粒まき、本葉1枚の頃生育の良いものを残して間引いて1本にし、本葉4、5枚まで育てます(図1)。
[畑の準備]
植え付け2週間前に1平方m当たり苦土石灰100gを全面にまいて耕します。次に、畝幅(ベッド幅)90cmで、中央に深さ20cm程度の溝を掘ります。この溝1m当たり化成肥料(NPK各成分10%)100gと堆肥2、3kgとを施し、溝を埋め戻して高畝を作ります(図2)。
[植え付け]
遅霜の心配のない4、5月が植え付け適期で、株間90cm程度に植え穴を掘り、穴に十分水を注いで植え付けます。遅霜の恐れのあるときは、ポリフィルムでトンネル、ホットキャップやあんどんを作り、保温します(図3)。
[整枝・交配]
本葉5枚くらいで摘心し、生育の良い子づるを3本伸ばし、他の子づるはかき取ります(子づる3本仕立て)。伸びた子づるは重ならないように配置します(図4)。着果節位は10節前後を目標にし、雄花開花日の早朝に花粉を雌花の柱頭になすり付け、受粉(人工受粉)させます(図5)。
[追肥・敷きわら]
追肥は果実がこぶし大の頃、化成肥料を1株当たり30g程度、株元から離してばらまきます。茎葉と果実への泥はね防止のため、敷きわらや不織布など透水性の資材を敷きます。
[収穫]
開花後45~50日たって果実に爪が立たないくらい堅くなった頃が収穫適期です。収穫後7~10日、風通しの良い場所に置いておくと甘味が増します(図6)。
※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成しています。
【野菜もの知り百科】ローズマリー(シソ科マンネンロウ属)
土壌医●藤巻久志
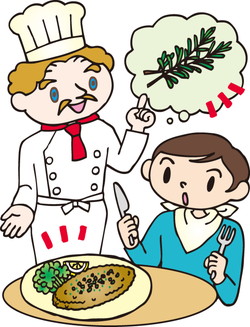 ローズマリーは常緑低木のハーブです。一般に野菜は一年草の草本作物なので、木本作物のローズマリーは野菜ではないかもしれません。副食にするために栽培する植物は野菜という考えもあります。ハーブは香味野菜とも呼ぶので、ローズマリーを取り上げることにしましょう。
ローズマリーは常緑低木のハーブです。一般に野菜は一年草の草本作物なので、木本作物のローズマリーは野菜ではないかもしれません。副食にするために栽培する植物は野菜という考えもあります。ハーブは香味野菜とも呼ぶので、ローズマリーを取り上げることにしましょう。ハーブという言葉が広く使われるようになったのは、1970年に開催された日本万国博覧会(大阪万博)からです。欧米の国々が出店したレストランで、数千万の来場者がフレッシュやドライのハーブを使った料理を食べました。和食にはない風味でした。それまで庶民が食べてきたコロッケやポークカツレツなどの洋食には生のハーブは入っていませんでした。
ハーブはラベンダーやセージなど地中海沿岸原産のシソ科植物が多く、石灰質を含んだ土質を好みます。ローズマリーも同じで、属名Rosmarinusのrosは露を、marinusは海を意味し、海岸の崖にも自生します。
ローズマリーには立性型と匍匐(ほふく)型があり、花色は淡紫、青、桃、白などがあります。暑さ寒さ、乾燥、病害虫に強いハーブです。ベランダでも大型プランターで簡単に栽培でき、種や挿し木で増やします。葉は殺菌や酸化防止の効果があり、魚介や肉料理の風味付けなどに利用します。香りが強いので使用量に注意します。茎はバーベキューの串やリースなどにします。
ローズマリーは欧州で古くから利用されてきたハーブです。英国民謡『スカボロー・フェア』では「パセリ・セージ・ローズマリー・アンド・タイム」と何回もリフレインされています。サイモンとガーファンクルがカバーした『スカボロー・フェア』は、67年のダスティン・ホフマン主演の映画『卒業』の挿入歌となり、世界中で大ヒットしました。当時のほとんどの日本人は、歌詞のうちパセリしか食べたことがありませんでした。
藤巻久志(ふじまきひさし)
種苗管理士、土壌医。種苗会社に勤務したキャリアを生かし、土づくりに関して幅広くアドバイスを行う。
シニア野菜ソムリエKAORUのベジタブルライフ
メロン - 贈答用の定番「フルーツの王様」
シニア野菜ソムリエ ●KAORU

KAORU
日本野菜ソムリエ協会公認 シニア野菜ソムリエ
ラジオ局で報道キャスターを務める傍ら、野菜ソムリエの資格を取得。全国で第1号の野菜ソムリエとなる。現在は日本野菜ソムリエ協会の講師として野菜ソムリエの育成に力を注ぐ他、TV・ラジオ・雑誌などでも活躍。セミナーや講演、執筆活動も行っている。飲食店のレシピ開発や大手企業とのコラボ商品も多数手掛ける。大好きな野菜・果物について語る時間は何よりも幸せなひととき。
著書に『干し野菜手帖』『野菜たっぷり!サンドイッチレシピ』(共に誠文堂新光社)、『ポケット版 旬の野菜カレンダー』(宝島社)などがある。
私の食育日記
親子でパン作り
食育インストラクター●岡村麻純
 ある朝娘が、私が作ったパンを食べながら「パンって何からできているの?」と聞くので「強力粉と砂糖、塩、水、後はドライイーストとバターがあればできるよ」と答えると、作ってみたいと言うので、早速親子でパン作りを始めました。今回はホームベーカリーには頼らずに頑張りました。
ある朝娘が、私が作ったパンを食べながら「パンって何からできているの?」と聞くので「強力粉と砂糖、塩、水、後はドライイーストとバターがあればできるよ」と答えると、作ってみたいと言うので、早速親子でパン作りを始めました。今回はホームベーカリーには頼らずに頑張りました。
小麦粉の中でもタンパク質含量の高いものを強力粉、少ないものを薄力粉、その中間のものを中力粉と呼びます。パンを作る場合は主に強力粉を使います。娘にとっては粉と水を混ぜるだけでもちもちになるのが不思議なようで、グルテン形成の説明をしました。グルテン形成とは、小麦粉に水分を加えて練ることで、小麦粉の主なタンパク質であるグリアジンとグルテニンが絡み合って、でんぷんを内部に取り込んだ網目のような塊ができることです。そこに加える塩はこのグリアジンの粘性を増し、グルテンの網目を緻密にするのを助けます。また、砂糖は安定性を高めます。バターは風味や、パンの耳のサクッとした食感を作ります。こうしてできた塊、つまり生地を酵母の力で膨らませて焼くことでパンが出来上がります。
娘は発酵によって膨らんでいくのが面白かったようで、少し過発酵になってしまいましたが、自分たちでこねて作ったパンは何よりおいしかったようです。
家庭で作るときには、材料を一度に混ぜて作る、直捏(じかごね)法という作り方をすることが多いのですが、大手のパン屋さんなどでは、まず材料の半分以下を生地にして発酵させ、後から残りの材料を加えてこねる、中種(なかだね)法で作るのが一般的です。こちらの方が、パンが大きく膨らみ、ふっくら柔らかくなるそうです。最近は「実験だよ」と言いながらキッチンに立つのが好きな娘と、次は中種法にもチャレンジしてみようと思います。
岡村麻純(おかむら ますみ)1984年7月31日生まれ。お茶の水女子大学卒。大学で4年間食物科学を学び、食生活アドバイザーなどの資格を持つ。公式ブログ:http://ameblo.jp/masumiokamura/
出典:JA広報通信2022年3月号
← 令和4年2月号
令和4年4月号 →