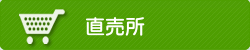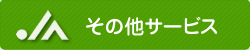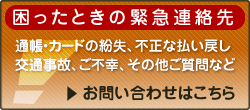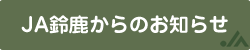[楽しい園芸] [野菜のルーツ] [豆知識&簡単レシピ] [食の健康百科] [バックナンバー]
楽しい園芸 – プロから聞いたアドバイスを紹介。初めての人もおまかせ! –
【あなたもチャレンジ!家庭菜園】 鮮度が命のホウレンソウは自家菜園取りが最良
板木技術士事務所 ●板木利隆
 西アジアが原産で世界各地に広がり、日本へは東洋種が中国から、その後西洋種がヨーロッパから伝わり、現在は両者の交配種が主流で、品種改良により新品種が次々とお目見えしています。
西アジアが原産で世界各地に広がり、日本へは東洋種が中国から、その後西洋種がヨーロッパから伝わり、現在は両者の交配種が主流で、品種改良により新品種が次々とお目見えしています。カロテンやミネラルが豊富で、緑黄色野菜の中でも栄養価は抜群。鉄・マグネシウム・マンガン・亜鉛などのミネラル類、ビタミンB1・ビタミンC・葉酸などを豊富に含み、貧血予防にも有効とされています。
葉物野菜の中でもホウレンソウは鮮度が命、葉先から水分がどんどん蒸発してしまうので、取りたての新鮮なうちに調理したいもの。家庭菜園取りが大変魅力的です。
畑の準備に当たっては、ホウレンソウは酸性土壌を最も嫌う作物であること(好適pHは6・3~7・0)を心得、石灰を多めに施用することと、畑の周囲の排水を図り、まき溝に水たまりしないように、凹凸なく丁寧に作るようにします。
まきどきは春先のトンネル栽培の2月上旬(関東南部の平たん地、以下同じ)から10月中旬までの広範にわたりますが、ホウレンソウは低温には強い(生育停止温度は0度だがマイナス10度までは寒害を受けない)のですが、高温には比較的弱い(30度になると生育停止)こと、日長が長い時期(13時間以上)あるいは外灯の照明下などにまくと、とう立ちすることをよく認識してまきどきを選ぶことが大切です。
露地栽培で育てやすいのは9月上旬から10月上旬の秋冬取りと、3~5月の初夏取りです。ただし、春まきは長日条件に入るので、春まき用の晩抽性(とう立ちしにくい品種)を選ぶことが大切です。
ホウレンソウの種子は堅い果皮の殻に包まれていますので、過湿の畑では果皮が水を吸い過ぎ、内部が酸欠になり発芽しにくくなってしまいます。多雨の後はまき溝に水たまりしていないか気配りをしましょう。発芽しやすいように果皮を取り除いたり、削って薄くした種子も販売されています。これらは発芽しやすいですが、種子を保護する力が弱いので、乾燥期には発芽するまでの灌水(かんすい)を怠らないように注意しましょう。本葉2枚で間引いて株間を2cmほどになるようにし、株元に少し土寄せします。その後1~2回間引きして、最終株間を6~7cmとし、草丈5~6cmのころと10cmぐらいのころ、条間に化成肥料と油かすを追肥し、中耕して土を和らげます。草丈が20cmぐらいになったら収穫適期です。
四季の花づくり 今が時期、土の若返り
●早川 京子
 寒い時期で、水分を多く必要としない時期であっても草花は、根を働かせ、水分を使っています。水分が不足すると生育や春の開花に影響を及ぼすことがありますので、水やりを忘れないようにします。土の表面が乾いてきたら、水やりをしますが、苗状態のものは、ほぼ定期的にやるのがよいでしょう。わらや落ち葉、枯れ草、芝の刈りくずなどがあれば、マルチしておくと、乾燥防止とともに、地温の大きな低下も防げます。
寒い時期で、水分を多く必要としない時期であっても草花は、根を働かせ、水分を使っています。水分が不足すると生育や春の開花に影響を及ぼすことがありますので、水やりを忘れないようにします。土の表面が乾いてきたら、水やりをしますが、苗状態のものは、ほぼ定期的にやるのがよいでしょう。わらや落ち葉、枯れ草、芝の刈りくずなどがあれば、マルチしておくと、乾燥防止とともに、地温の大きな低下も防げます。
宿根草は間もなく根が動きだしますので、肥料を与えておきます。野菜くずや果物の皮などを株の周りに埋めておくだけでもいいでしょう。緩効性肥料を混ぜておけばさらにいいでしょう。
根が動きだすのが他の宿根草より早いサクラソウは、2月上旬くらいから、株分け、植え付けをします。
春植え草花の花壇の準備をしておきましょう。土を深く起こして、下層の土を表層に出す天地返しをして、酸素不足になった土を生き返らせてやりましょう。このとき、消石灰を1平方m当たり100g程度、混ぜておきます。酸性化した土の矯正のためです。植え付けの1カ月くらい前になったら、土をさらに砕き、堆肥や元肥を入れて、準備をします。
鉢物を育てる計画なら、花壇作業の少ない今の時期に、土と腐葉土、肥料を混ぜ合わせた培養土を作っておくと、栽培時期に慌てないで済むでしょう。
昨年秋から始めた水栽培のヒヤシンスなどは、もうしっかり寒さに当たっているはずですから、暖かくしてやっても立派に花が咲くはずです。立春過ぎくらいから、室内など暖かい、日当たりの良い場所に移して、開花を迎える準備をしましょう。
ベジフル歳時記・野菜のルーツ – 身近な野菜のルーツをご紹介します –
節分
野菜ソムリエ ●KAORU
 節分の日には鬼(邪気)をはらうため豆まきをします。鬼とは姿の見えない災い全般のこと。悪魔のような鬼の目=魔目(まめ)を目掛けて豆を投げ、魔を滅する=魔滅(まめ)という意味があると考えられているのです。鬼が嫌いなヒイラギの枝に焼いたイワシの頭を刺し戸口に立てておく、また自分の年の数だけ豆を食べるなどの風習は受け継がれ、実践している方も多いでしょう。
節分の日には鬼(邪気)をはらうため豆まきをします。鬼とは姿の見えない災い全般のこと。悪魔のような鬼の目=魔目(まめ)を目掛けて豆を投げ、魔を滅する=魔滅(まめ)という意味があると考えられているのです。鬼が嫌いなヒイラギの枝に焼いたイワシの頭を刺し戸口に立てておく、また自分の年の数だけ豆を食べるなどの風習は受け継がれ、実践している方も多いでしょう。
節分における行事食を見てみると、豆を食べる以外にもあれこれ挙げられます。関東の主流はけんちん汁。ダイコン・サトイモ・ゴボウ・ニンジンなど旬の根菜類や豆腐などをたっぷり使い、基本的には動物性タンパク質を入れずにいただきます。
関西では大阪発祥の恵方巻きが定番。近年では関東にもその文化が浸透し、全国的に定着しています。年神様がいるとされる縁起の良い方角、恵方に向かって恵方巻きを無言で丸かじりすると、一年を健康で過ごすことができるのだとか。恵方巻きとは福を巻き込む太巻きずしで、7種の具を使うことが主流のようです。商売繁盛や無病息災を願い、七福神にちなんで7種になったという説が有力。家庭で作るときには、かんぴょう・キュウリ・シイタケなどお決まりの具も魅力ですが、せっかくですから春の訪れを告げるナバナ・ミツバ・セロリ・アスパラガスなどを利用するのもお勧めです。
さらに四国では砂おろしといってこんにゃくを食べる風習があり、大みそかと同様そばを食べる地域も多いようです。また昆布・梅入りのおめでたい福茶に豆を入れて飲むことも。
地元ならではの食材や旬の野菜を取り入れたオリジナルの節分料理で、家族そろって会話を楽しみながら、日常で不足しがちな野菜類も補いましょう。
豆知識・簡単レシピ – 旬の食材の豆知識やレシピを紹介します –
新鮮食材で楽しくクッキング① キャベツとカキの豆乳スープ
料理研究家 ●波多野充子
 |
■材料(2人分) 1食当たり約188kcal
カキ ……………… 大6個(約120g) |
|
■ 作り方
海のミルクと呼ばれるほど栄養豊富なカキと、野菜がたっぷりの豆乳スープです。カキが白くなってきたら豆乳を加え、温まれば完成です。この時期ならではのおいしいスープをお楽しみください。 |
|
新鮮食材で楽しくクッキング② ラビオリ風・エビとレンコンのワンタン
 |
■材料(3人分) 1人分約197kcal
エビ …………………………… 160g 調味料 |
|
■ 作り方
ツルっと滑らかなワンタンはビッグサイズ。イタリアンのラビオリのように、2枚の皮を合わせるだけで簡単に出来上がります。具材はとてもヘルシーですので、お好きなタレを付けてたっぷりお召し上がりください。 |
|
ベターホームのお料理教室
冬野菜の代表格。寒い時期に甘味が増します - ダイコン –
 ダイコンは一年中出回っていますが、寒い時期に甘味が増しておいしくなります。日本では、春の七草の一つ「スズシロ」として古くから、親しまれています。 現在は肉質が柔らかく、甘味が強い青首ダイコンが主流ですが、京都の伝統野菜の聖護院(しょうごいん)ダイコン、水分が多く大型の三浦ダイコン、薬味に使われる辛味ダイコンなど、独自の品種があります。シャキシャキとした食感を生かし、生のままサラダやあえ物、大根おろしとして食べたり、加熱すると甘味が増し、だしのうま味を閉じ込めるので、ぶり大根、おでんなどの煮物や煮込み料理、スープにしたりと、いろいろな料理でおいしくいただけます。 葉の付け根の部分は甘く、先端(しっぽ)ほど辛味が強くなるので、料理によって使い分けるのがポイント。生で食べるときは葉に近い部分、煮物など加熱する料理には真ん中の部分、先端はみそ汁などに使うとよいでしょう。 ダイコンに含まれる辛味成分は、がん予防に効果があるといわれ、ビタミンCも豊富です。その他、消化を助け、胃腸の働きを整えて食欲をアップさせるジアスターゼも含まれています。ジアスターゼは加熱すると壊れてしまうので、生のまま食べる方が効果的です。脂っぽいものを食べるときに大根おろしを添えると、消化も良く、さっぱりします。 選ぶときは、太くて重いもの、皮に張りがあるものが新鮮です。葉が付いているものは、そのまま置いておくと、葉から水分が失われスカスカになってしまうので、葉を切り分けて保存します。使いかけのものは、乾燥しないように切り口をラップで覆い、ポリ袋に入れて、野菜室へ。葉の部分はゆでて刻んで冷凍しておくと、みそ汁の青味や煮物の彩りにもなり、便利です。
ダイコンは一年中出回っていますが、寒い時期に甘味が増しておいしくなります。日本では、春の七草の一つ「スズシロ」として古くから、親しまれています。 現在は肉質が柔らかく、甘味が強い青首ダイコンが主流ですが、京都の伝統野菜の聖護院(しょうごいん)ダイコン、水分が多く大型の三浦ダイコン、薬味に使われる辛味ダイコンなど、独自の品種があります。シャキシャキとした食感を生かし、生のままサラダやあえ物、大根おろしとして食べたり、加熱すると甘味が増し、だしのうま味を閉じ込めるので、ぶり大根、おでんなどの煮物や煮込み料理、スープにしたりと、いろいろな料理でおいしくいただけます。 葉の付け根の部分は甘く、先端(しっぽ)ほど辛味が強くなるので、料理によって使い分けるのがポイント。生で食べるときは葉に近い部分、煮物など加熱する料理には真ん中の部分、先端はみそ汁などに使うとよいでしょう。 ダイコンに含まれる辛味成分は、がん予防に効果があるといわれ、ビタミンCも豊富です。その他、消化を助け、胃腸の働きを整えて食欲をアップさせるジアスターゼも含まれています。ジアスターゼは加熱すると壊れてしまうので、生のまま食べる方が効果的です。脂っぽいものを食べるときに大根おろしを添えると、消化も良く、さっぱりします。 選ぶときは、太くて重いもの、皮に張りがあるものが新鮮です。葉が付いているものは、そのまま置いておくと、葉から水分が失われスカスカになってしまうので、葉を切り分けて保存します。使いかけのものは、乾燥しないように切り口をラップで覆い、ポリ袋に入れて、野菜室へ。葉の部分はゆでて刻んで冷凍しておくと、みそ汁の青味や煮物の彩りにもなり、便利です。
RECIPE ダイコンと牛肉のスープ
 撮影:大井一範 撮影:大井一範 |
■材料(2人分) 一人分約88kcal
ダイコン ………………………………………… 150g A B ※花しょうは中華食材で、粒さんしょうのことです。
|
|
■ 作り方(調理時間 15分 ※漬け置く時間は除く)
|
|
出典:JA広報通信2014年1月号
平成26年2月号 →