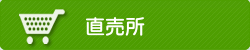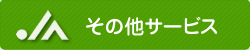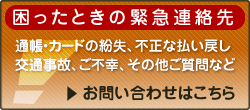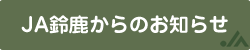[楽しい園芸・野菜のルーツ] [ベジタブルライフ] [私の食育日記] [バックナンバー]
楽しい園芸 – プロから聞いたアドバイスを紹介。初めての人もおまかせ! –
【あなたもチャレンジ!家庭菜園】ニンニク – 適期に植え付け、追肥と灌水を行う
園芸研究家 ●成松次郎
 中央アジア原産と推定されるヒガンバナ科の多年生草本で、生育適温は15~20度、暑さに弱く、寒さには比較的強い野菜です。栽培は秋に種球を植え付け、初夏に収穫します。
中央アジア原産と推定されるヒガンバナ科の多年生草本で、生育適温は15~20度、暑さに弱く、寒さには比較的強い野菜です。栽培は秋に種球を植え付け、初夏に収穫します。
強い香りの成分は硫化アリルで、体内で豊富に含むビタミンB1と結合すると疲労回復効果があります。
[品種]
温暖地向きでは「平戸」「嘉定」「上海」など、「ニューホワイト六片」は寒冷地から弱暖地にも向く品種です。
[畑の準備]
植え付け2週間前までに、1平方m当たり苦土石灰200gを施して土に混ぜておき、1週間前に化成肥料(NPK各成分10%)100gと完熟堆肥を2kg施します。その後、幅70~100cmの畝(ベッド)を作り、穴の間隔が15cm程度の黒マルチフィルムを張ります(図1)。
[植え付け]
9月上旬ごろに休眠が明けてくるので、種球を小片(鱗片:りんぺん)にばらし(図2)、寒冷地では9月中旬~10月上旬、温暖地では9月下旬~10月中旬に植え付けます。小片頂部を上にマルチ穴(15cm間隔)に深さ5cm程度に浅く植えます(図3)。
[わき芽かき]
芽出し後に1株から2芽以上出たときは、生育の良い1芽を残して、手で早めにかき取ります(図4)。
[追肥・花蕾(からい)摘み]
成長が再開する翌春2月と3月に1平方m当たり化成肥料50g程度を追肥しますが、マルチ栽培では所々穴を開けておきます。とう立ちしてつぼみが付いたら、球の肥大に影響があるため花蕾を早めに摘み取ります。畑の乾燥に弱いため、特に春先からの灌水(かんすい)が必要です。
[収穫]
初夏になり、葉が半分くらい枯れたら、晴天日に抜き取って根を切り落とし、畑で2~3日乾かします(図5)。その後、茎を30cmほど残して切り取り、10球程度を束ねて風通しの良い軒先などにつるします(図6)。
※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成しています。
【野菜もの知り百科】ラッカセイ(マメ科ラッカセイ属)
土壌医●藤巻久志
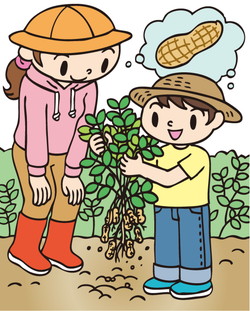 ラッカセイは漢字では「落花生」と書きます。開花後に子房柄(しぼうへい)が地中に侵入し、サヤを作る不思議な植物です。ラッカセイの完熟子実(ピーナツ)は食用作物に分類され、野菜の本には載らないこともあります。未熟子実(ゆでラッカセイ)は野菜ですが、全世界の生産量はごくわずかです。
ラッカセイは漢字では「落花生」と書きます。開花後に子房柄(しぼうへい)が地中に侵入し、サヤを作る不思議な植物です。ラッカセイの完熟子実(ピーナツ)は食用作物に分類され、野菜の本には載らないこともあります。未熟子実(ゆでラッカセイ)は野菜ですが、全世界の生産量はごくわずかです。ラッカセイは南米原産で、コロンブスの新大陸発見後に欧州、アフリカ、アジアで栽培されるようになりました。日本には18世紀初頭に中国から伝わったので、南京豆と呼ばれました。
ラッカセイの花は一日花で、早朝に開花して午後にはしぼみます。マメ科野菜の花はチョウの形をしていて、魅力的な物が多いです。家庭菜園では春には薄紫色のソラマメの花、夏には黄色のラッカセイの花、秋には水色のシカクマメの花が楽しめます。
殻の表面に浮き上がっている筋は維管束で、水や栄養分の通り道です。維管束は子実が熟してくるとはっきりとしてきます。ラッカセイの完熟子実の収穫は、葉が黄変した頃に株ごと引き抜いて乾かします。ゆでラッカセイはその20日くらい前に収穫し、すぐに利用します。
殻は中の子実を守るために堅いです。石灰は土壌酸度を改良するために栽培の前に施しますが、細胞壁を強くする効果もあります。ラッカセイのサヤの充実には石灰が必要で、石灰が不足すると未熟サヤや空サヤが多くなってしまいます。産地では開花後に石灰を散布し、畑が真っ白になることもあります。
「黒ラッカセイ(ブラックピーナツ)」はサヤに子実が2~4粒入ります。一般の品種は1粒入りもありますが、ほとんどは2粒入りの双子です。双子の歌手といえばザ・ピーナッツ。1959年のデビュー曲『可愛い花』のB面は『南京豆売り』です。どちらも世界的ヒットのカバー曲です。
藤巻久志(ふじまきひさし)
種苗管理士、土壌医。種苗会社に勤務したキャリアを生かし、土づくりに関して幅広くアドバイスを行う。
シニア野菜ソムリエKAORUのベジタブルライフ
ナメコ - 独特のぬめりが特徴のキノコ
シニア野菜ソムリエ ●KAORU

KAORU
日本野菜ソムリエ協会公認 シニア野菜ソムリエ
ラジオ局で報道キャスターを務める傍ら、野菜ソムリエの資格を取得。全国で第1号の野菜ソムリエとなる。現在は日本野菜ソムリエ協会の講師として野菜ソムリエの育成に力を注ぐ他、TV・ラジオ・雑誌などでも活躍。セミナーや講演、執筆活動も行っている。飲食店のレシピ開発や大手企業とのコラボ商品も多数手掛ける。大好きな野菜・果物について語る時間は何よりも幸せなひととき。
著書に『干し野菜手帖』『野菜たっぷり!サンドイッチレシピ』(共に誠文堂新光社)、『ポケット版 旬の野菜カレンダー』(宝島社)などがある。
私の食育日記
お庭で野菜作り
食育インストラクター●岡村麻純
 わが家のお庭で、野菜作りを始めました。大きなプランターを使ったコンテナ栽培です。子どもたちと一緒に苗や種から選び、それぞれに担当を決めてお世話は責任を持ってもらい、上のお兄ちゃんには、その野菜について調べることもお願いしました。
わが家のお庭で、野菜作りを始めました。大きなプランターを使ったコンテナ栽培です。子どもたちと一緒に苗や種から選び、それぞれに担当を決めてお世話は責任を持ってもらい、上のお兄ちゃんには、その野菜について調べることもお願いしました。
夏には、ピーマン、ニンジン、ミニトマトにエダマメ、息子の希望で小玉スイカにもチャレンジしました。どれも身近な野菜ばかりでしたが、実際に育ててみると新しい発見がいっぱい。息子は雄花と雌花の違いを知り、「野菜にも、お父さんお母さんが必要なんだ、家族だったんだね!」と感動していました。
そして、何カ月もかけて育ててみた子どもたちの感想が、「野菜って、なかなか食べられるようにならないね。やっとできたのにこれだけ?」というものでした。まさに、これが、私が感じてほしかったことです。スーパーに行けば山積みにされている野菜たち。1袋にたくさん入っているプチトマト。野菜といえばその姿ばかり見てきた子どもたちにとって、毎日見つめてもなかなかできず、やっとできても、子ども2人で味見するほどしかできないことに衝撃があったようです。
食育活動において、野菜作りは定番のカリキュラムです。苦手な野菜を自分で作ったら食べられるようになった、そんな話もよく聞きます。それはとってもすてきなことです。でも、私が食育で最も伝えたいことは、食べ物が自分自身をつくっているということを理解して、食べることを大切にする。食べ物があるということに感謝して、食べ物を大切にする。この二つです。
子どもたちは、自分が時間をかけて作ったわずかなトマトを、胃に入っていくのを意識しているかのように、とっても味わって食べていました。その食べ物をいとおしむ感覚を知ってほしい、それが1番の願いでした。
さて、次の季節は何を育ててみようかなと家族会議が始まっています。
岡村麻純(おかむら ますみ)1984年7月31日生まれ。お茶の水女子大学卒。大学で4年間食物科学を学び、食生活アドバイザーなどの資格を持つ。公式ブログ:http://ameblo.jp/masumiokamura/
出典:JA広報通信2021年8号
← 令和3年7月号
令和3年9月号 →